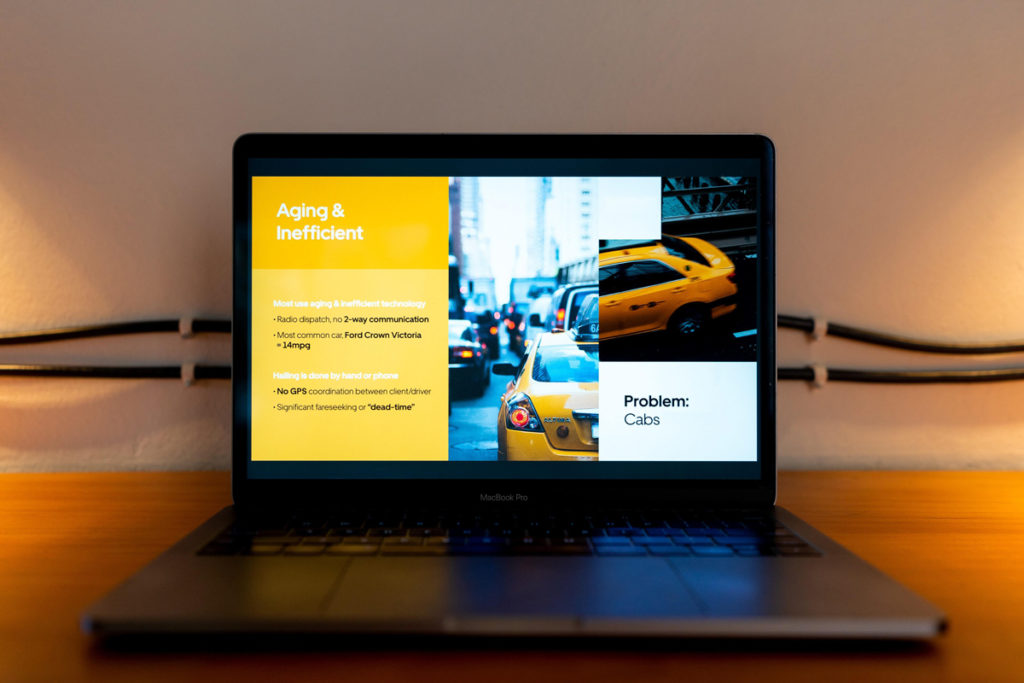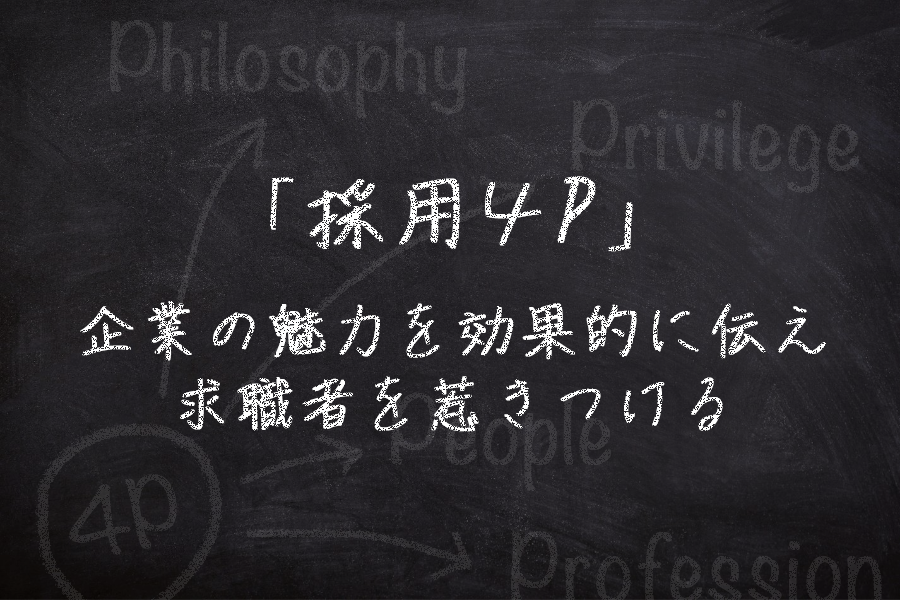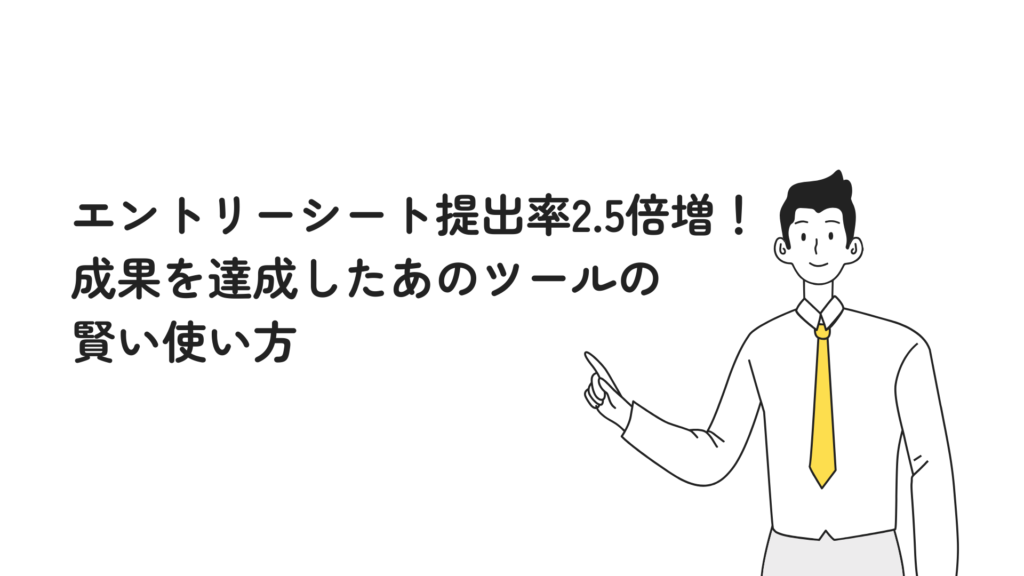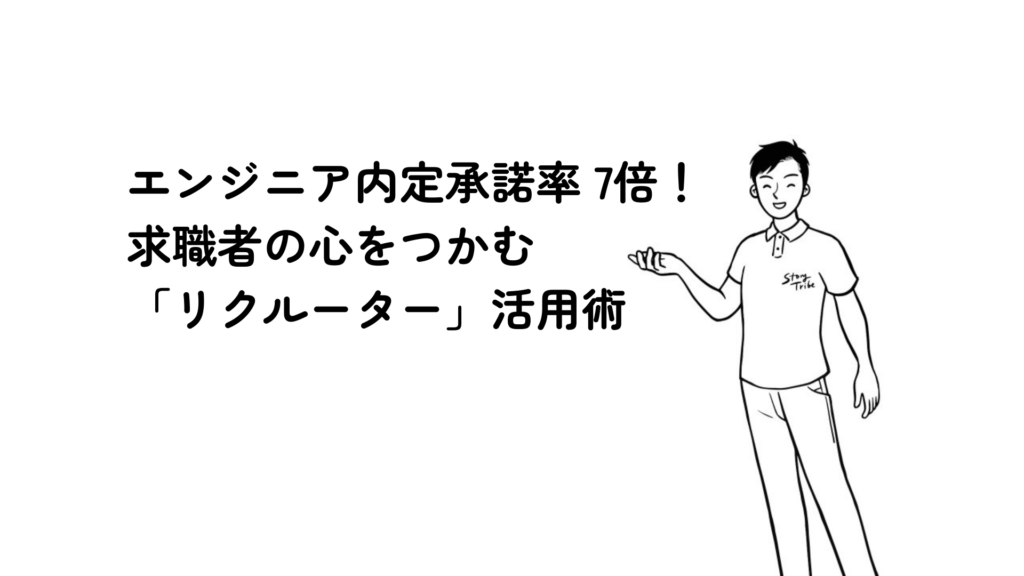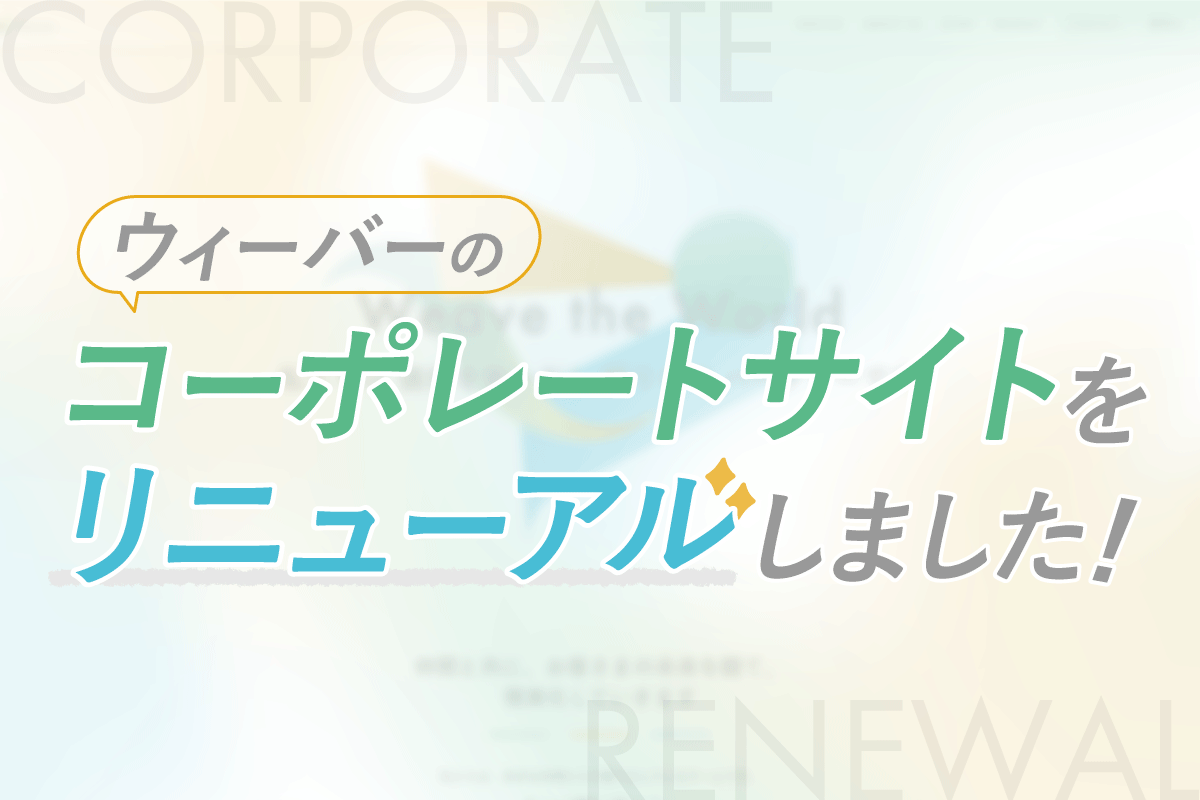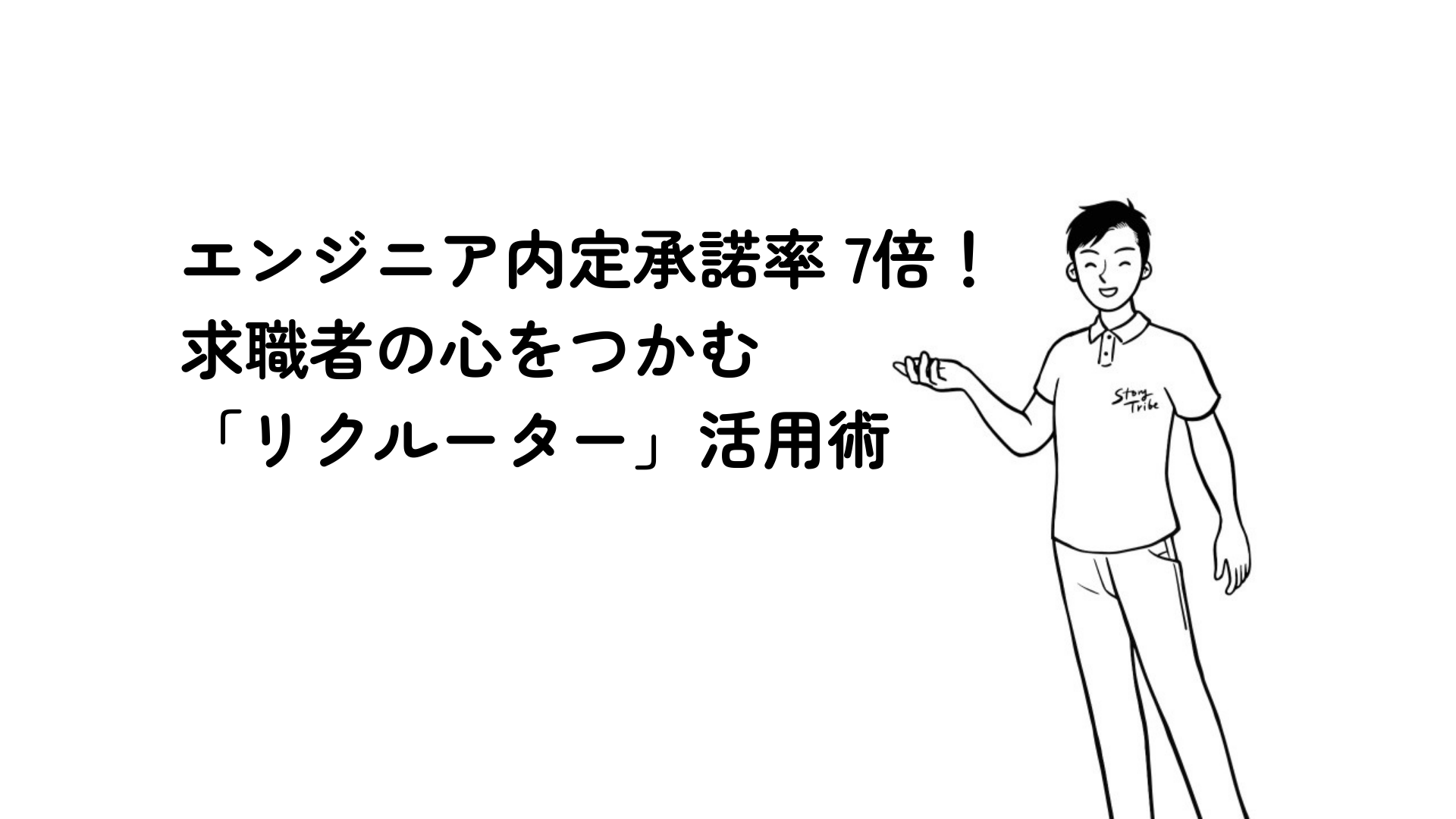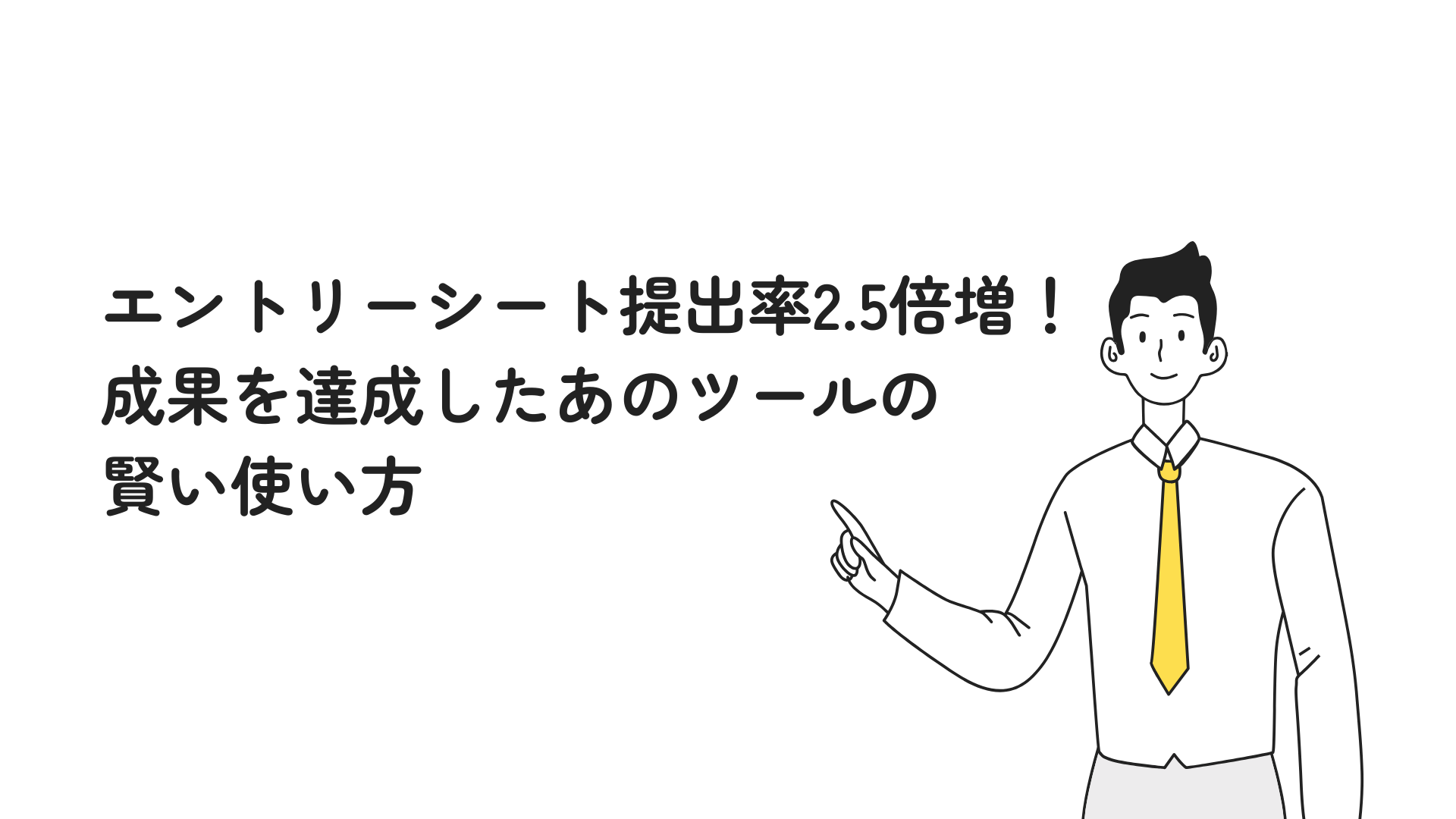今回は『採用ピッチ資料』の作成の仕方や、作成時のポイントについて紹介していきます。
- 「そもそも採用ピッチ資料って何だっけ?」
- 「採用ピッチ資料を作りたいけど、何から手をつけていいか分からない・・。」
- 「どんな手順で作成していくといいの?」
など、初めて作成する方に参考にしていただければ嬉しいです。
『採用ピッチ資料』とは?
採用ピッチ資料の“ピッチ”とは、「短いプレゼンテーション資料」という意味です。そのため採用ピッチ資料とは、そのまま訳すと「自社の採用について短くプレゼンテーションする資料」となります。
通常の会社説明資料は、会社概要、事業やサービス説明などのスライドがあります。一方で採用ピッチ資料には、「(ターゲットとする求職者にとっての)自社の魅力」「求める人物像」「働く環境」「(採用背景にも関係する)今後の課題」などの情報が盛り込まれていることが特徴です。
更に近年、人事や採用関係者などの間では、採用ピッチ資料はオンライン上で公開されていることが当たり前になっています。オンライン上で公開することにはメリットがたくさんあるので後述します。そして採用ピッチ資料のボリュームは、がっつり50ページ以上、非常に濃い内容が用意されているケースも多く、当初の「ピッチ→短く」は薄れているような気もします。
これまでの会社説明資料の問題点を解決する3つのポイント
従来の会社説明資料の問題点として、下記が挙げられます。
- 会社概要、事業やサービス説明などの情報があるが、求職者が求める情報(採用情報)が少ない
- 自社の魅力などの「会社のいいことろ」、求める人物像などの「会社が伝えたいこと」だけが記載してあり、求職者が知りたい情報(現状の問題点や今後の課題などリアルな情報が足りていない
- 資料データは採用関係者が保有しているため、自社社員が最新の採用情報を確認しにくい(リファラル採用で活用しにくい)
特に、情報のリアルさ、新鮮さがないと表面上だけの情報となってしまい、求職者は会社の内側について知ることができません。入社してから「説明と聞いていたのと全然違う・・」というギャップを感じてしまうこともあります。
これは社外だけではありません。社内、つまり自社の社員への情報共有がしにくいと、採用活動に対する社員の理解も浅くなり会社としての認識が一致せず、リファラル採用での協力を得るのが難しくなります。
そこで、これらの問題点を解決するために、『採用ピッチ資料』を作成し利用する会社が増えています。採用ピッチ資料では大きく分けて3つのポイントがあります。
1.求職者が必要とする情報を盛り込む
よく、営業で使っている会社説明資料を、そのまま採用活動でも使っているケースが見受けられます。採用ピッチ資料では、例えば「組織図、採用ポジション」「評価制度、給与体系」「採用背景、求める人物像」「働く環境、仕事でよく使うツール」などの求職者が求めていそうな情報を盛り込んでいきましょう。
2.リアルな部分まで ありのまま 誠実に伝える
採用ピッチ資料では、極力、会社の内側のリアルな部分まで具体的に記載するようにします。
例えば、現状の事業あるいは組織上の問題や今後の課題点(解決策)などを追記したり、“一緒に働きたい人”だけでなく“一緒に働きたくない人”まで入れる企業も増えています。
このように表面上だけの情報だけではなく、会社のリアルな部分を詳細に記載することで、自社がターゲットとする求職者からの共感や理解を得やすくなります。
3.資料はオンライン上に公開。社内外に情報を共有
採用のオープン化が進んでおり、自社の情報をより積極的に発信する企業が多くなってきました。オンライン上に公開することで応募者の目につきやすくなり、応募前の事前のスクリーニング(ふるい分け)にも繋がります。よりターゲットとなる人とのマッチングを高め、応募後の選考プロセスにおける歩留り向上や効率アップが期待できます。
面談/面接前には資料を事前に読み込んできてもらうことで、会社説明の時間コストカットや、応募者の会話にフォーカスしてより一歩踏み込んだ話をすることができます。例えば面接時間を通常の60分から30分に減らす施策なども可能になります。
また、オンライン上に資料を公開することで、応募者だけでなく自社社員へ採用活動の内容を共有できることも大きなメリットです。全社員が自社の採用を理解してリファラル採用でも活用しやすくなり、社員の認識統一も図ることができます。
参考になる企業の採用ピッチ資料をまとめておりますので、よろしければご参考にどうぞ↓
それでは次に採用ピッチ資料の作成の流れを説明していきます。
採用ピッチ資料の作成の流れ
作成はグループワークで行うとベター
グループワークで進めていくことをオススメします!
なぜなら、会社のリアルな部分を作成する資料のため、人事・採用担当者だけでなく、様々なメンバーから意見を聞いて作成することが大切だからです。
新卒社員、中堅、役職者、それぞれから数名の社員をピックアップしてチームを作ります。カジュアル面談、一次面接、最終面接などに関わるメンバーで認識を統一させることも重要です。全社員を巻き込んで一緒に作成していきましょう。
グループワークの進め方
グループワークの流れ、準備する物は下記になります。
(流れ)
- 資料項目を選ぶ
- 新しく追加する項目と改善が必要な項目の議論
- 追加/改善項目 列挙
- 追加/改善項目をグルーピング(カテゴリ分け)
- カテゴリの題名を言語化
- カテゴリ、コンテンツの優先順位を決める
- グループワークを基にコンテンツを資料にまとめる
- 完成!(情報をオンライン上にオープン)
(準備する物)
- ポストイットや用紙(意見を書く用)
- 筆記用具
- ホワイトボードまたは広めの壁(グルーピングする際に書いたポストイットを張る場所)
※ポストイットは、グルーピングする際に壁やホワイトボード等に貼り付けることができ、視覚的にまとめられるので便利です。
イメージはこんな感じです。↓
では各項目で押さえておきたいポイントを流れに沿って説明していきます。
グループワークをする時に押さえておきたいポイント
1.資料項目の選定
説明資料の構成を設定します。現状の説明会資料の項目と内容を確認し、そこから新しい採用ピッチ資料に追加する項目や改善、削除する項目を書き出していきます。
参考までに項目例を紹介します。
〈項目例〉
◼会社紹介・事業紹介
- 会社概要
- ミッション・ビジョン・バリュー
- 事業概要・事例
- 新規事業/新規サービス
◼組織図・企業文化
- 創業者の想い
- 組織人員体制図
- バリュー(価値観、文化)
- 自社ならでは魅力
- 今後の課題
- 福利厚生
- 研修、教育、能力開発
- 画像で見る当社(社内風景など)
- データで見る当社
◼求人情報
- 組織図
- 採用背景
- 採用ポジション
- こんな人と働きたい
- こんな人は見送りたい
- 業務の詳細(役割、業務内容、KGI/KPI)
- ポジション別のメンバー紹介
◼そのほかの情報
- 給与体系
- インセンティブ
- ストックオプション
- 給与体系
- 年収例
- 評価制度
- マーケット情報
- 選考フロー
- よくある質問
上記は基本的な構成項目になりますが、もちろん上記以外の項目を追加していただいても大丈夫です。自社のオリジナリティがあればあるほど、他社との差別化に繋がります。
2,追加/改善項目 議論
ここでは、各項目ごとに下記の流れでグループワークを進めるとよいです。
- 項目の列挙
- 似たような項目をグルーピング
- グルーピングしたコンテンツを言語化(一言で表すと?)
項目を列挙する際は、ポストイットに一つずつ意見を書いてもらい、ホワイトボード等に貼っていくと、グルーピングがしやすくなります。
では、資料項目の例より「自社の魅力」「今後の課題」「一緒に働きたい人/働きたくない人」の3つを例に、やり方を説明していきます。
長丁場になると思いますので、適宜に休憩を取りながら行ってください!
例1)自社の魅力
自社の魅力をアピールすることで、求職者の入社意欲や入社後のマッチング度を高められることや経営陣&社員&採用メンバーの認識を一致させることができます。
まず、項目の列挙です。自社の魅力について、社員のみなさんから一つずつポストイットに書き出してもらいましょう。どんな小さなことでもOKです。
ある程度出してもらったら、似たような項目をグルーピングしていきます。ここでは採用4Pを参考にすると分けやすいです。
〈採用4P〉
- Philosophy(理念・目的)
- Profession(仕事・事業)
- People(人材・風土)
- Privilege(特権・待遇)
グルーピングをしたらカテゴリーの題名を決めます。それぞれのカテゴリーで一番伝えたいことは何なのか言語化することが大切です。
例2)現状の問題、今後の課題(解決策)
現状の問題、今後の課題はしっかりと押さえておきたいポイントです。ここはデリケートな内容になりますので、社員に意見を書き出してもらったポストイットは、誰が何を書いたか分からなくなるようにします!
しかしながら経営者の前では言いづらい部分もあるかと思います。そこでグルーピングをする際は、一旦経営陣の皆さんは席を外していただき、社員のリアルな声をまとめていくのも良いでしょう。
問題・今後の課題点をグルーピングする際は、短期で解決が可能なもの、長期で解決を目標とするもの、社員に受け入れて欲しいもの(今後も同じもの)などに分けていくと課題がより明確になり言語化しやすいです。
このようにグルーピングをしていくことにより、具体的な問題を確認することができます。まとめた内容は経営陣に共有し、今後の課題(解決策)を一緒に考えてもらうようにしましょう。
現状の問題や課題を取り入れる事により応募者の入社後のマッチング度を高められたり、経営陣&社員&採用メンバーの認識一致、当事者意識を持ったり等のメリットに繋がります。
例3)一緒に働きたい人/働きたくない人を決める
ここでは一緒に社員として働きたい人、働きたくない人を書き出していきます。求職者の「スクリーニング」と「入社後のマッチング」、経営陣&社員&採用の「認識の一致」を図ることを目的としています。
一緒に働きたい人、働きたくない人とは、人間性やコミュニケーション、価値観の目線で書く項目になります。
会社のバリューや面接シートの項目(学習意欲が高い?倫理的?情熱的?人間性は?等)を参考にしたり、現在一緒に働いている人たちはどんな人が多いかなど振り返ってみたりすると書き出しやすいです。
3.カテゴリの優先順位を決める
各項目グルーピングと言語化ができたら、記載する内容の優先順位を決めます。優先順位を決めることで、会社が大切にしていることや方向性等社員間の認識統一をすることができます。一項目において優先順位の上位3~5つ(目安)ぐらいが丁度いい文量になるかと思います。
4.採用ピッチ資料 作成
言語化した内容を纏めていきましょう。文章だけだと見づらいので、コンテンツに合った写真、データがあれば尚良いです。
まとめ

グループワーク、お疲れ様でした!
グループワークは正直とても時間がかかりますが、その分他企業にはない自社オリジナルの等身大の資料を作ることができます。そのリアルさ、誠実さのある内容が今の求職者には響く大きなポイントなのだと思います。
ぜひ、作成する際に今回の記事が参考になれば嬉しいです。
弊社では採用ピッチ資料の作成のお手伝いもさせていただいております。企業様にヒアリングをさせていただいた後、資料の作成のご支援をいたします。
もしご興味がある方はお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

ウィーバー株式会社は「色とりどりの持続社会」を理想に描き、「価値あるカタチに織りなす」ことを使命としています。「人・組織・事業の成長パートナー」として、転職および採用支援、マーケティング支援、メディア運営支援サービスを提供しています。